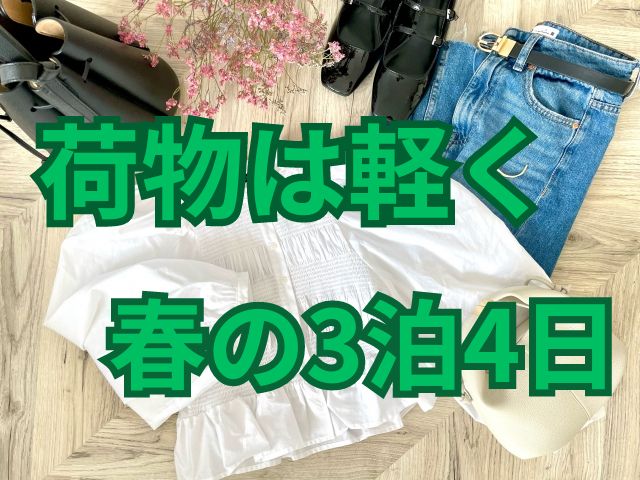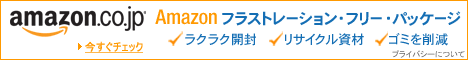\50秒で読めます/
春といえば、桜や新生活など前向きなイメージが強い季節です。しかし一方で、気分が落ち着かず、なんとなく憂うつになるという人も少なくありません。春になるとイライラしやすくなったり、メンタルが不安定になったりする人が増えており、その背景には気候や生活環境の変化、ホルモンバランスの乱れなど、さまざまな原因が隠れています。この記事では、春が嫌いと感じる理由を具体的に整理し、春の不調やストレスを少しでも和らげるためのヒントをまとめています。春に心や体が揺らぎやすい方に、共感と実用的な対策をお届けします。
- 春が嫌いと感じる心理的・身体的な理由
- 春特有のストレスや不調の具体的な要因
- 春を快適に過ごすための生活習慣や工夫
- 同じように春が苦手な人の傾向や特徴
春は嫌いと感じる人が増える理由
春は気温差が大きく、自律神経が乱れやすい季節です。さらに進学や転勤など環境の変化が集中し、心身にストレスがかかります。花粉症や気圧の変動による不調も重なり、イライラや憂うつを感じやすくなります。そのため、春が嫌いと感じる人が増えるのです。

春はなぜイライラしやすいのでしょうか?
春になると、なんとなく気分が落ち着かず、普段よりもイライラしやすくなる人が増えます。その背景には、いくつかの環境的・身体的な要因が複雑に絡んでいます。
まず大きいのが「自律神経の乱れ」です。春は気温の変化が激しく、寒暖差が日によって、あるいは1日の中でも大きくなります。こうした外的な変化に体がついていこうとすると、自然とストレスがかかり、自律神経が乱れがちになります。これが、イライラや不安感を引き起こす原因の一つです。
また、春は「環境の変化」が最も多い季節でもあります。進学・進級・転勤・引っ越しなど、新しい人間関係や生活スタイルに適応しようとするだけで、精神的な負荷が大きくなります。期待や希望に満ちた雰囲気のなかに、「取り残される感覚」や「焦り」が潜んでいることも、感情が不安定になる要因です。
さらに「日照時間の変化」も影響しています。日が長くなる春は、活動的になれる一方で、ホルモンバランスが乱れやすい時期。特に「セロトニン」と呼ばれる精神を安定させる物質の分泌が不安定になると、感情のコントロールが難しくなり、怒りっぽく感じることもあります。
これに加えて、春は「花粉症」や「気圧の変動」など、身体的にも不快感を感じる要素が多いため、知らず知らずのうちにストレスをため込みやすくなります。
つまり、春は身体と心の両面から負荷がかかりやすい季節。その結果、イライラや不調を感じる人が多くなるのです。イライラの正体がわかれば、自分を責めずに対策がしやすくなります。
春になるとメンタル不調になるのはなぜ?
春は「心が軽くなる季節」と思われがちですが、実際には気分が落ち込んだり、やる気が出なかったりと、メンタル面の不調を感じる人が少なくありません。その原因には、いくつかの心理的・身体的な影響が重なっています。
まず注目したいのが、「生活や人間関係の変化」です。春は進学や就職、異動、引っ越しなど、環境の変化が集中する時期です。これらの出来事はポジティブなものであっても、無意識にストレスとして心に負担をかけます。特に新しい人間関係に慣れるまでの間は、緊張感が続き、心が休まりにくくなります。
加えて、「季節の変わり目による体調の不安定さ」も大きな要因です。寒暖差や気圧の変化は、自律神経のバランスを崩しやすく、心と体のつながりからメンタルにも影響を及ぼします。なんとなく疲れやすい、眠りが浅いといった症状が続くと、気分も落ち込みやすくなります。
また、「春特有の孤独感」を感じる人もいます。世間が新しいスタートに浮かれている雰囲気に対して、自分が取り残されているような感覚を持つことがあります。このズレが、焦りや虚しさを呼び起こし、精神的な不調につながるケースも見られます。
さらに、女性の場合は「ホルモンバランスの変化」により、季節の影響をより強く受けやすい傾向もあります。花粉症や肌トラブルといった身体の不調が重なると、ますます気分が沈みやすくなります。
このように、春のメンタル不調には、外部環境の変化・気候・体調・社会的なプレッシャーなど、さまざまな要素が複合的に関わっています。自分だけが調子が悪いわけではないことを理解し、ゆっくりと心と体を整えていくことが大切です。

春は嫌い 花粉がもたらす影響
「春が嫌い」と感じる大きな理由の一つに挙げられるのが、花粉症の存在です。春はスギやヒノキなどの花粉が多く飛散する季節で、毎年多くの人がくしゃみ・鼻水・目のかゆみといった不快な症状に悩まされています。
花粉症の症状は、単なる鼻や目のトラブルにとどまらず、日常生活や精神状態にも大きな影響を与えます。まず、「集中力の低下」が顕著になります。鼻づまりや目のかゆみで睡眠の質が下がったり、頭がぼーっとしたりするため、仕事や勉強に集中できないと感じる人も多いです。
また、「外出するのが億劫になる」という声もよく聞かれます。天気が良い日でも花粉が多いと分かると、外に出るのがストレスになり、活動量が減ってしまいます。これにより、気分が沈みやすくなり、春を楽しむ余裕が持てなくなってしまうのです。
さらに、花粉症による「慢性的な疲労感」も見逃せません。体がアレルゲンに反応している状態が続くと、常にどこか不快でエネルギーが奪われたような感覚になります。このだるさや重さが、気分の落ち込みやイライラを引き起こし、「春=つらい季節」という印象につながってしまいます。
花粉の影響は、直接的な症状だけでなく、間接的に心身のバランスを崩す原因にもなります。そのため、花粉症の人にとって春は「憂うつ」「疲れる」「避けたい」と感じやすく、春を嫌いになる一因として大きな影響を持っているのです。

春の寒暖差と気候の不安定さ
春は「三寒四温」とも言われるように、寒い日と暖かい日が交互に訪れ、気温が安定しません。この寒暖差が体調や気分に与える影響は想像以上に大きく、「春が嫌い」と感じる原因の一つとなっています。
特に日中と朝晩の気温差が激しいことで、体は常に環境に適応しようと働き続け、自律神経が乱れやすくなります。自律神経は体温調節や睡眠、気分の安定などに関わる重要な働きを担っており、そのバランスが崩れると、だるさや頭痛、不眠、イライラなどの不調があらわれやすくなります。
また、春には「春一番」や「突風」「急な雨」など、天候の変動も激しく、予測が難しいのが特徴です。朝晴れていたのに急に雨が降ったり、強風で砂ぼこりが舞ったりと、外出がストレスに感じる日も多くなります。
こうした天候の不安定さは、体調だけでなく気持ちにも影響を及ぼします。予定通りに行動できないことが続いたり、服装選びに毎朝悩んだりすることで、小さなストレスが積み重なっていきます。
さらに、春は気圧の変化も大きく、気象病(気圧の変動によって頭痛やめまいが起きる症状)を引き起こす人も少なくありません。特に敏感な人にとっては、春の気候そのものが心身の不調の引き金になることもあります。
このように、春の寒暖差や天気の不安定さは、心と体のバランスを崩しやすく、「なんとなく調子が悪い」と感じる状態を引き起こします。気候が安定する初夏まで、「春が嫌い」と感じる人が多いのも、こうした理由によるものです。
春の雰囲気 嫌いと感じる背景
春といえば、桜が咲き、新生活が始まり、明るく前向きな雰囲気が広がる季節です。しかし、そうしたポジティブな空気感そのものを「苦手」「嫌い」と感じる人もいます。これは決して珍しいことではなく、春独特の“明るさ”や“期待感”に対する心理的な違和感が背景にあります。
まず、「周囲の空気と自分の気持ちのギャップ」が挙げられます。春は一般的に「新しいことにチャレンジする時期」「リスタートの季節」といった前向きなイメージが強調されますが、自分自身がその流れに乗れないとき、取り残されたような感覚や焦りを感じやすくなります。「なぜ自分だけ前向きになれないのか」と自分を責めてしまうこともあります。
また、「人間関係の変化」も春の雰囲気を重く感じさせる要因です。卒業や転勤、クラス替えなどで別れと出会いが交錯し、感情が不安定になりやすい時期でもあります。そうした別れの多い季節特有の“切なさ”や“寂しさ”が、春を嫌う理由になることもあるのです。
加えて、「社会全体の期待ムード」もプレッシャーになります。たとえばSNSやメディアでは、春に向けたファッション・メイク・ライフスタイルの特集が多く見られますが、それらが自分にとって無理のある理想像に感じられると、自己否定や疲れを誘発しがちです。
春の雰囲気は、希望にあふれている反面、「明るさを求められる圧力」を感じさせる一面もあります。それに共鳴できないとき、「春が嫌い」と感じるのは、ごく自然な心の反応と言えるでしょう。自分のペースで季節を受け入れていくことが、心を穏やかに保つヒントになります。
春に感じる人間関係のストレス
春は新しい出会いや別れが多く、人間関係における変化が激しい季節です。その変化こそが、目に見えないストレスの大きな原因となり、多くの人が春を「疲れる季節」「居心地が悪い」と感じるきっかけになっています。
特に進学・就職・転勤・異動といった節目では、これまで築いてきた人間関係がリセットされ、新しい環境での関係づくりが求められます。こうした変化は、社交的な人にとっても負担ですが、内向的な人や人見知り傾向がある人にとっては、大きなプレッシャーになります。
また、初対面の人との距離感をつかむまでには時間がかかるため、「無理に明るくしなきゃ」「うまくやらなきゃ」といった“良い人”を演じようとする意識が強まり、気疲れすることも多いです。相手に合わせすぎたり、本音を言えないまま関係を築こうとすることで、心が消耗していきます。
さらに、送別会や歓迎会など、春特有のイベントが続くことも、コミュニケーションに対するストレスを増幅させる要因です。人と関わる時間が増える一方で、自分の時間や心の余裕が奪われることで、「一人になりたい」「誰とも話したくない」と感じることもあるでしょう。
加えて、学生時代のクラス替えや、子どもの進学に伴う保護者同士の付き合いなど、春には年齢や立場に関係なく、人間関係の構築が求められる機会が自然と増えていきます。この「知らないうちに気を遣う時間の増加」が、ストレスとして蓄積されていくのです。
春の人間関係におけるストレスは、“頑張らなければ”という無言のプレッシャーから生まれがちです。そのため、自分のペースを大切にし、少しずつ関係を築いていくことが、春を少しでも穏やかに過ごすコツになります。

春が嫌いな人に知ってほしい対策
春が嫌いな人は、無理に前向きになろうとせず、自分のペースを大切にすることが大切です。生活リズムを整え、睡眠・食事・軽い運動を習慣にすることで、心身の安定につながります。また、情報や人付き合いに疲れたら距離を置き、安心できる空間や時間を意識的に確保しましょう。

春が苦手な人におすすめの過ごし方
春がどうしても苦手だと感じる人にとっては、「頑張って楽しもう」とするよりも、無理をせず、自分にとって心地よい過ごし方を選ぶことが大切です。春特有の不調や不快感をやわらげるために、日常の中でできる工夫をいくつかご紹介します。
1. 生活リズムを安定させる
春は気温の変化や新生活のスタートなどで、生活リズムが乱れがちです。就寝・起床時間をできるだけ一定に保ち、食事や運動も毎日同じ時間帯に行うことで、自律神経のバランスが整いやすくなります。とくに朝の光を浴びる習慣は、体内時計をリセットし、気分の安定にもつながります。
2. 外出は「無理のない範囲」で
人混みや花粉、強風など、春の外出にはストレスがつきものです。外に出ることがしんどいときは、無理をせず、近所を少し歩く、ベランダで日光を浴びるなどの“軽い外気浴”がおすすめです。自然と触れ合うことで、ストレスホルモンの分泌が抑えられ、リラックス効果が期待できます。
3. 春の情報から距離を置く
SNSやテレビでは「春の新生活」や「ポジティブな変化」が頻繁に取り上げられますが、それが逆にプレッシャーになることもあります。必要以上に情報に触れず、自分のペースで過ごす時間を意識的に作ることが、心の安定につながります。
4. 香りや音でリラックスする
春のざわざわした空気が苦手な人は、アロマや音楽など、自分にとって落ち着ける感覚を取り入れてみましょう。ラベンダーやベルガモットなどの香りは気分を鎮めてくれる作用があり、ゆったりした音楽や自然音もメンタルの調整に効果的です。
5. やらないことを決める
春は「始める季節」というイメージがありますが、無理に新しいことを始める必要はありません。むしろ「やらないことリスト」を作って、頑張りすぎを防ぐほうが、春を楽に乗り切ることができます。手を抜ける家事や断るべき誘いを明確にしておきましょう。
春が苦手という気持ちは、決しておかしいことではありません。自分を責めず、「無理をしない」「自分に合った過ごし方を選ぶ」ことが、春をやり過ごす大切なポイントになります。
春が一番嫌いな人の特徴と傾向
「春が一番嫌い」と感じる人には、いくつか共通する傾向や特徴があります。これは単なる好みの問題ではなく、季節が持つ特性と、その人の体質・性格・ライフスタイルとの相性によって起こる自然な反応とも言えます。
1. 環境の変化が苦手な人
春は新学期や異動、引っ越しなど、社会的に“変化”が多い季節です。そのため、環境の変化に敏感な人や、新しい人間関係への適応にストレスを感じやすい人にとっては、非常に負担の大きい時期になります。
2. 感覚が鋭い・繊細な人(HSP気質など)
気温・湿度・光・音・においなど、春に起きるあらゆる変化に過敏に反応してしまう人も、春を苦手としやすいです。特に「暖かくなってきたのに心が晴れない」というズレに対して、違和感を覚えやすくなります。
3. 自律神経が乱れやすい人
春の寒暖差や気圧の変動により、自律神経のバランスが崩れると、疲れやすさや気分の落ち込みが強くなります。こうした身体的な反応から、「春になると体調が悪い=春が嫌い」と結びつくことがあります。
4. プレッシャーを感じやすい真面目な人
春は「新しいことを始めなきゃ」「何か変わらなきゃ」という空気が強くなりがちです。それに対して真面目な人ほどプレッシャーを感じやすく、気づかないうちに心が疲弊してしまいます。
5. 花粉症や季節性アレルギーがある人
花粉や黄砂による身体的不調が強い人も、春に対してネガティブな印象を持ちやすいです。目・鼻・喉などの症状が毎年続くことで、春が来ること自体が憂うつに感じられるようになります。
6. 過去に春に嫌な記憶がある人
卒業、別れ、失敗など、過去に春にショックな出来事を経験していると、その記憶と季節が結びつき、「春=つらい季節」として定着してしまうケースもあります。
こうした特徴に当てはまる人は、春の明るく希望に満ちた雰囲気に共感できず、むしろ心がざわつく傾向があります。「春が嫌い」と感じることは特別なことではなく、自分自身のペースや感受性を大切にしている証とも言えるのです。

春の体調不良をやわらげる習慣
春は「なんとなく不調が続く」と感じやすい季節です。寒暖差・花粉・気圧の変化・新生活のストレスなど、体と心の両方に影響を与える要因が重なることで、頭痛、だるさ、眠気、めまい、胃腸の不調などが起こりやすくなります。そんな春特有の体調不良をやわらげるために、日常生活の中で意識したい習慣をご紹介します。
1. 朝の光を浴びて体内リズムを整える
起床後はカーテンを開けて、できるだけ自然光を浴びましょう。朝の光は、睡眠や体温、ホルモン分泌をコントロールする「体内時計」をリセットする役割があります。眠気が取れやすくなるほか、気分の落ち込み予防にもつながります。
2. 服装で寒暖差に対応する
春は日によって気温差が10度以上になることもあります。薄手の服を重ね着して、脱ぎ着しやすいスタイルを心がけましょう。首元や足元を冷やさないことも、自律神経を安定させるポイントです。
3. 栄養バランスを意識した食事
疲れが溜まりやすい春こそ、タンパク質・ビタミンB群・鉄分など、エネルギー代謝を助ける栄養素を意識して取りましょう。コンビニ食や軽食ばかりになると、疲労感や集中力の低下につながります。
4. 軽い運動で血流を促す
散歩やストレッチ、軽い筋トレなどの習慣は、血行を促進し、体のこわばりや気分のモヤモヤをやわらげてくれます。激しい運動でなくてOK。「体を動かすこと」が大切です。
5. 湯船に浸かってリセットする
シャワーだけで済ませず、ぬるめのお湯にゆっくり浸かることで、自律神経のバランスが整いやすくなります。1日10分~15分の入浴でも、緊張をほぐし、疲れが取れやすくなります。
6. 「がんばらない日」をつくる
体調が揺らぎやすい春に、毎日全力で過ごすのは逆効果です。意識的に予定を減らす日、何も予定を入れない日を作り、心身の余白をつくることで、疲労や不調の蓄積を防ぐことができます。
春は誰にとっても変化が多い季節。体調不良を「仕方ないこと」として受け止めつつ、無理せず整える習慣を取り入れることで、少しずつ春との付き合い方が変わってくるかもしれません。
春の気分の落ち込みを軽減する方法
春は心が明るくなる季節と思われがちですが、実際には「なんとなく気分が沈む」「やる気が出ない」と感じる人が多くいます。寒暖差や環境の変化、ホルモンバランスの乱れなどが重なり、気分の落ち込みにつながりやすい時期です。そんな春特有のメンタルの揺らぎを軽くするために、取り入れたい習慣や工夫をご紹介します。
1. 睡眠時間をしっかり確保する
春は生活リズムが崩れがちで、知らず知らず睡眠不足になることがあります。疲れやすさやイライラ、落ち込みを防ぐためにも、1日7~8時間を目安に睡眠を取るよう心がけましょう。特に「いつもより眠い」と感じる日は、無理に動かずしっかり休息を。
2. 深呼吸と軽いストレッチを習慣に
不安や緊張を感じやすいときは、呼吸が浅くなりがちです。意識して深呼吸をしながら軽いストレッチを取り入れることで、副交感神経が働き、気分がゆるやかに落ち着いてきます。朝や寝る前の5分だけでも効果的です。
3.「何もしない時間」を作る
春は“新しいことを始めなきゃ”という無言の圧力を感じやすい時期ですが、あえて何もせず、ぼーっとする時間を持つことも大切です。公園のベンチに座る、窓から景色を眺める、ゆっくりお茶を飲む——そんな何気ない時間が、心のリセットにつながります。
4. ネガティブを否定せず受け入れる
「春なのに元気が出ない自分」にダメ出しをしないことも大切です。気分の波は自然なものだと受け止めることで、心が軽くなります。「今はこういう時期」と一歩引いて眺めるだけで、自分への負担を減らすことができます。
5. ちょっとした“うれしい”を増やす
大きな目標を立てるよりも、気分が少し上がる瞬間を意識して増やすのがポイントです。お気に入りの飲み物を買う、気になる本を読む、好きな音楽を流すなど、小さな喜びを日々に散りばめましょう。
6. 心の状態を人と比べない
SNSなどでは「春を満喫している人」の投稿が目に入りやすく、自分が取り残されたような気持ちになることもあります。ですが、気分や体調の波は人それぞれ。「あの人はあの人、自分は自分」と距離をとって見ることが、気持ちを守る手助けになります。
春は「心が浮き立つ季節」というイメージが強い分、気分が落ち込むとギャップが大きく感じられるものです。でも、自分に合ったペースで穏やかに過ごすことで、春の過ごしにくさも少しずつ和らいでいくはずです。

春の変化に無理なく適応するには?
春は、気温や天候、環境、生活リズムなどが一気に変化する季節です。進学・就職・異動・引っ越しなど、外的な変化に対応しなければならない場面も多く、知らず知らずのうちに心身が疲れてしまうことがあります。春の変化に無理なく適応するためには、意識的に“自分を守る”工夫が必要です。
1. 「完璧に慣れよう」としない
新しい環境では、すぐに適応できないのが当たり前です。「早く馴染まなきゃ」と自分にプレッシャーをかけるほど、ストレスが溜まりやすくなります。まずは“慣れなくても大丈夫”という気持ちで、できることから一つずつ進めていく意識が大切です。
2. スケジュールに余白を持たせる
春は予定が増えがちですが、毎日をギュウギュウに詰めると、気づかぬうちに疲れが蓄積していきます。移動時間や休憩時間など、あえて「何もしない時間」をスケジュールに組み込むことで、変化への抵抗感が和らぎます。
3. 小さな“いつも通り”を残す
すべてが新しくなると、心の拠り所がなくなってしまいます。たとえば「朝食のメニューは変えない」「毎晩同じ音楽を聴く」など、自分にとって落ち着ける“いつもの習慣”を意識的に残すことで、心が安定しやすくなります。
4. 頼れる人や場所を見つけておく
環境の変化に不安を感じたとき、すぐに話を聞いてもらえる人や、安心できる場所があると心がラクになります。無理に人間関係を広げようとせず、まずはひとりでも「安心できる存在」を見つけておくことが、気持ちの支えになります。
5. 気分の変化を記録する
日記やメモ、スマホのアプリなどで、自分の気分や体調の変化を記録してみましょう。「この時期は落ち込みやすい」「天気の悪い日は調子が悪い」など、自分の傾向が見えてくると、対処しやすくなります。
6. 自分の“適応ペース”を受け入れる
周りの人がスムーズに新生活に馴染んでいるように見えても、比べる必要はありません。適応に時間がかかるのは悪いことではなく、自分に合ったペースで動くことが、結果的には心と体を守ることにつながります。
春の変化は避けられないものですが、「変わる環境に合わせる」だけでなく、「自分の心地よさを保つ」という視点を持つことで、無理なく過ごしやすくなります。頑張りすぎず、少しずつ“春に慣れていく”スタンスで構いません。

春の不調を和らげる生活リズムの工夫
春は寒暖差や気圧の変動、環境の変化などが一気に押し寄せる季節です。体がその変化に対応しきれず、自律神経が乱れやすくなることで、頭痛・だるさ・不眠・イライラなどの「春の不調」を感じやすくなります。そんな不調をやわらげるためには、生活リズムを少し工夫することが大切です。
1. 毎朝決まった時間に起きる
体内時計を整える基本は「起きる時間を固定すること」です。寝る時間よりも起きる時間を一定にすることで、ホルモンの分泌や体温のリズムが安定し、日中の集中力や夜の眠気もスムーズに整ってきます。
2. 朝日を浴びて体をリセットする
起きたらまずカーテンを開けて、自然光を浴びましょう。朝の光は、脳を目覚めさせるスイッチになります。10〜15分程度、ベランダや玄関先に出るだけでもOKです。
3. 食事は1日3回、決まった時間に
春の不調は、胃腸の働きの乱れとも深く関係しています。できるだけ毎日同じ時間に食事をとることで、体のリズムが整いやすくなります。朝食を抜くと体温が上がりにくくなるため、簡単でも何か口に入れるようにしましょう。
4. 日中は軽く体を動かす
春はだるさから動きたくなくなることもありますが、あえて少し体を動かすと、血流が良くなり、気分もスッキリします。通勤時に一駅歩く、昼休みに軽くストレッチするなど、無理のない範囲でOKです。
5. 夜はスマホから離れてリラックス
寝る直前までスマホやパソコンの画面を見ていると、脳が覚醒して寝つきが悪くなります。夜は照明を少し落とし、ゆったりした音楽や読書など“光を浴びない時間”を意識的に作ると、質の良い眠りにつながります。
6. 週末に「整える日」を設ける
忙しい平日で乱れた生活リズムは、週末に一度リセットしましょう。寝すぎや夜更かしをせず、心と体を整える意識で過ごすと、翌週もスムーズにスタートできます。
春の不調は、毎日のちょっとした習慣の積み重ねで軽減できます。リズムを整えることは、体の不調だけでなく、気分の安定にもつながる大事なケア。完璧を目指すより、自分が無理なく続けられるペースで整えていきましょう。
まとめ春が嫌いと感じる人
- 春は気温差が激しく、自律神経が乱れやすい
- 日照時間の変化でホルモンバランスが崩れやすい
- 環境の変化が集中し、精神的ストレスが増える
- 花粉症の症状が集中力や睡眠の質を下げる
- 外出を避けたくなり、活動意欲が低下しやすい
- 春の雰囲気がプレッシャーや孤独感を引き起こす
- 天候の急変が多く、予定や気分が乱されやすい
- 春特有のイベントが人間関係のストレスを生む
- 春は体と心の両方に負荷がかかりやすい時期である
- 真面目な人ほど「頑張らなければ」と無理をしがち
- 敏感な気質の人は春の刺激に疲れやすい傾向がある
- 過去の出来事と春を結びつけて苦手意識が残ることもある
- 睡眠・食事・運動のリズムを整えることが重要である
- 春の情報やSNSから距離を置くことが心を守るコツである
- 無理をせず、自分のペースで過ごす工夫が必要である
 AIによる要約です
AIによる要約です春が嫌いと感じる人は、気温差や花粉、環境の変化によるストレスなど、さまざまな要因に影響されています。自律神経やホルモンバランスの乱れが心身の不調を招き、イライラや落ち込みが起きやすくなります。この記事では、春の不調を引き起こす理由を解説しながら、生活リズムの整え方や心の負担を減らす工夫を紹介しています。同じように春が苦手な人の声や特徴もまとめており、共感と実用的な対策の両方を得られる内容です。